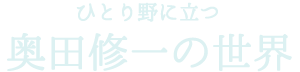画館便り
奥田が友の会の方々にお送りしている季節の便り(風景画館便り)の中から抜粋しております。
年数回新しいエッセイを追加して参ります。
- 私の創作の原点は自然への愛である。
私の創作の原点は自然への愛である。人知れず咲く野の花に見とれることも、河原に無数に転がる石ころの一つを手に取って感心することも、創作に還元されて行くものだと思う。創作とは、ちょっとした人間的な思いや、行為の積み重ねの上に成り立つものである。歌人・窪田空穂は、「才能や努力、そういったものはあってもかまいませんが、なくたってかまいません。」と語った。才能や努力でさえ当てにならない。私もその通りだと思う様になった。
- 約束していた私の画をお届けに上がると
約束していた私の画をお届けに上がると、赤飯を炊いてお待ち頂いていた。有難かった。
- 本をほとんど買わない私は
本をほとんど買わない私は、近隣の市町村の図書館カードを三枚持っていて、交互に借りてきては、眠る前のひととき読書するのがささやかな楽しみになっている。
図書館では道立、県立はおろか、国会図書館の本までリクエスト出来る筈で、何一つ不自由を感じないばかりか、本が手元に残らないので有難い。こんな本も読んでみようかと先日ダライ・ラマの本を初めて読んだが、その最後に短い祈りの言葉があって、美しい言葉だと思った。こういうものになれますように、
今もこれからもずっと
保護をもたない人の保護役に
道に迷った人の案内役に
海を渡る人の船に
川を渡る人の橋に
危機に瀕している人の避難所に
明かりをもたない人の松明に
逃げ場をもたない人の隠れ屋に
そして、困っているすべての
人のしもべに
- 日本人が印象派贔屓なのは
日本人が印象派贔屓なのは、モネを代表とする様に、日本の浮世絵、また文化の影響を受けているので、何か自分達の感性に近いものを感じる点、またカンバスを戸外に持ち出し、身近な自然を描くのも共感するのだろう。また、ゴッホにおいてはそれのみにとどまらず、足元の虫を知らずにふみそうになる友人を止めて、「君が踏もうとしたのは神の創造物なのだ。」と言ったという話しだが、小さな虫の命も大切にする所は、良寛禅師が蚊帳から足を出して、蚊に血を吸わせた逸話などとも重なるところがある。生きとし生けるものへの愛情があって、その書簡集(ちょっと分厚い本数冊分ある)を読んだ人など、この人の誠実、苦悩、愛、悲しみには、胸を打たれた方も多いと思う。
私が好きなのはピサロ、シスレー、そしてゴッホ。また「ピカソが全ての画家の父」と呼んだセザンヌである。セザンヌがモネのことを「結局のところ、モネは単なる眼にすぎない。しかしなんと素晴しい眼だ。」と言い、ゴッホの画を見て、「はっきり申し上げるが、あなたは気が狂っておられる。」と言ったのは的を得ていると思う。
- 自然エネルギーを利用するなどと耳にすると
自然エネルギーを利用するなどと耳にすると、自然が自分達のもので、タダで使いたい放題の様な意味合いにも聞こえるが、実際は、自分達が自然の一部として、自然の恩恵の中に、かろうじて生かされていると言うのが本当の立場であろう。
庭にある十坪ほどの池には、冬になると厚さ数十センチの氷が張り、数十匹の鯉が池の底で冬を越す。水は摂氏四度が比重が一番重く、池の底にたまる。鯉は水温が1~2度位まで下がると死ぬ様だから、危うい自然のバランスの中で、かろうじて生き永がらえ、春を迎えている事になる。
ところがこの春は厳しい冬だったこともあってか、十匹ほど死んでいた。それらは皆、人間が品種改良した錦鯉で、真鯉や、その合の子は生き延びた。
- 芸術は作家(人間)と自然の間に
芸術は作家(人間)と自然の間にあるものだ。風景画家は、その事を意識する最たるものであろう。
画家の個性の多くは、自然と自分との間の、自分に近い所で描くか、それとも自然に近い所で描くかという事である。ところが本当は自分が自然の一部として、自然に身を委ねるほど一体になることが、作家の心を最も鮮やかに生かす事になる。
- 大ざっぱに言ってしまえば
大ざっぱに言ってしまえば、得意がって現代芸術などと言っているものは大抵インチキである。その判断は簡単である。作品に愛と美と命を感じるかである。芸術が人の心の不変の領域を扱うものだとすれば、それに過去も現在も未来もない。「新しい芸術はない。新しい芸術家がいるだけだ。」と言ったのは、エゴン・シーレだったろうか。シーレの芸術は、今も新鮮であり、人が人の心を持つ限り芸術であり続けるだろう。
たいてい作家は流行作家となる事を嫌う。その時代の大衆の味覚に合う様な作品を作る作家は、そのほとんどが忘れ去られる。何故なら大衆が芸術家に追いつき、その芸術を本当の意味で理解するのには時差が生じる。逆の言い方をすれば、時差こそあれ大衆は芸術を判断する能力がある。つまりは大衆一人ひとりが、愛と美と命を大切に思う心を持っていると言う事であり、芸術が人の心を扱うものだと言う事でもある。
- 私は自然を完全な絶対的存在として
私は自然を完全な絶対的存在として信じているので、それを捻じ曲げる科学の進歩という事については一部の医療・環境など分野を除いては大いに疑問がある。おおむかし、人が裸で暮らしている頃は、敵対する隣りの部族をやっつける為に、槍を尖らし柄を長くする様な事で良かった。ところが今は、一発の爆弾で、指先一つで、何万、何十万の人を抹殺できる。これを科学の進歩と言うのだろうか。進歩しなければならないのは科学ではなく、人間の方だと思うが、それが地球の運命を担う現在の指導者にもできない。人間自体が地球の一生物として欠陥がある様にさえ思える。拒否権を持つ大国の顔色を伺う国連などより、蟻にもメダカにも、種としての一票を割り振る地球連合の方が存在価値があるのではないか。
- マリアのクリスマス
マリアのクリスマス
クリスマスから正月までスペインの家内の実家で娘達と過ごした。義母のマリアは、家内から始めて紹介された二十年程前にはまだまだ元気で、私の靴が汚れているのを見付けると、「何をやっているのだ。」とサンダルを片手に家内を追いかけ回していた。
娘三人と息子一人に恵まれたが、一番下の家内が四歳の時、夫を失くす。咽頭癌だったと言う。今ならもう少し何とかなるのであろうが、バケツ半分も血を吐いて亡くなったと言う。八十半ばになった今でも、世の中で一番美しい名は夫の名ダネルだと言う。
マリアはその後、亡くなった姉の二人の男の子も引き取り、女手一つで六人の子供を育て上げた。そんな子供達がクリスマスの食事に集まる。夜の九時からのイヴのディナーが十人、翌日のランチはさらに三名増える。その料理を一手に作るのがマリア。それも並のフルコース以上の品数だから大変な手間である。それでも娘たちが手を出そうとすると「皆、私の味を食べに来るのだから余計な事をするな。」と手を出させない。イヴの昼頃になって、もう医者に行く位しか外出しなくなったマリアが、息子に運転をさせ、珍しく買物に出掛けて行き、ラムの骨付き肉など幾品か自分の眼で確かめて買い揃えて来た。料理の下拵えが終ると、少し休むと言ってソファでウトウトして、また料理にかかる。
皆が集まり、この日の為の特別なシャンパン、赤ワインなどを飲み始めたが、祝いのテーブルにマリアの席は用意されていない。一人台所で働き、料理が出来ると娘たちが運ぶ。時々料理の進み具合を見に来ては、二言三言話すとキッチンに戻る。良いタイミングで次から次へとバスク伝統の料理が出て、皆が次から次へと平らげて行く。デザートも終わって、皆がブランデーなどを飲み始めた頃、キッチンを覗くと、一人疲れ切ったマリアが座る背中が見える。小さなテーブルの上には、いつもの安ワインと余り物が少しばかり、私は声を掛けずに皆が陽気に笑いざわめく席に戻った。
- さよなら三角また来て四角
さよなら三角また来て四角
絵を描くと言うことは、自分の心と自然、カンバス、この三つの折り合いをつけて行くことである。自然から受けた感動の本質を自らの心に問い質し、カンバス上で確認すると言っても良い。ロダンが、「観たものをそのまま描く事を恐れるな、人は眼から手に行く間に心を通る。」と良い言葉を残しているが、「観たものをそのまま」と言うのは、人体を含め自然に対する絶対の信頼であろう。例えるなら親鸞聖人が、阿弥陀仏の本願ただ一つを信頼して、自らがまず救われた様なものだ。他力と言っても良い。
ゴッホなども創作には天上の光が必要だと言っている。自分の感性を押し付けるのではなく自然に縋り切ること、それが私の求める創作の方向性だ。
太宰が「自らを最も鮮やかに生かすのは献身である。」と言っているが、通じる所がある様に思う。将棋棋士の話を聞くと、何が何でも自分を押し通すのではなく、対戦の途中で相手に手を渡すことがあると言う。私は自然に手を渡しながら、自分の心を見詰め、カンバスの上に絵具をなすり付けるのが好きだ。
- 私は神を見たことがない。
私は神を見たことがない。しかし人々が神というものを、つまりは愛を、慎ましく生きる人々の、さりげない心の中に見て来たと思っている
- 涙を流すクリスト
涙を流すクリスト
もう二十年も使わない額がある。金の細やかな細工があり、荘厳すぎて私の風景画には合わない。宗教画が似合う額である。クリストを描きたい気がして来たので、その額のサイズのカンバスにした。青い背景の十字架に架かる傷だらけのクリストである。大分描き込んで、クリストの眼の下の芥子粒程の絵具のかたまりが気になり、パレットナイフで削ぎ落とすと、白いカンバスの地が現れた。まるで涙の様だと思った。クリストが涙を流している。私の描きたいのはこれだと思った。
- こんな歌がある
こんな歌がある
天地はすべて雨なりむらさきの花びら重れてかきつばた咲く
窪田空穂七十五才の歌である。この世界観に魅かれる。例えば木下利玄の、
牡丹花は咲き定まりて静かなり花の占めたる位置のたしかさ
なども好きな歌だが、花の背後に見え隠れする宇宙と言おうか、神と言おうか、それらまで写生されている。写生の極致と言って差し支えないだろう。私もそういうものに憧れ、描かなければならない年齢になった。
- 写生へ向う途中…
写生へ向う途中、丘を上る道を車で走っていると、アスファルトの上に、黒アゲハが落ちているのが眼に入った。車をバックさせ降り、捕まえようとするとバタバタと逃げるが、飛び立つところまでは行かない。車の中にあったビニール袋に羽根を傷めないように鋏み、元気になれば逃がそうと思った。
薄暗くなって家に帰ると庭に白い大きな牡丹が咲いている。この上で休ませようと置くとあまり抵抗することもなく落ち着いた。蜂蜜を水で溶き、スプーンで口に近づけるが飲まない。仕方がないので、葉の上にそれを付けて、その気があれば飲める様にした。
次の朝になると花の上にいないので辺りを探すと、草むらに落ち細かく震えていた。花の上に戻すが昨日よりさらに弱っている。夕方帰るまで生きているかと思ったが、帰ればまさに、虫の息でわずかに震えていた。
暗くなると、牡丹の白い花が徐々に閉じ始める。真っ暗になってから見に行くと、黒アゲハは羽先がほんのわずか見えるまでに白い花にしっかりと包み込まれている。白き花が死に行く虫をまさに抱いているのである。自然とは物凄いことをするものだとあらためて思った。構図も何も決まってないが、これなら描けると確信を持った。創作とはそういうところから始まる。
- 魔性
魔性
いつの頃だったのだろう。二十歳を少し過ぎた頃だったろうか。私はとある都内デパートの屋上で錦鯉やら川魚、小鳥や草木を販売しているのを冷やかしていた。東京広しと言えども、自然が好きな私の立ち寄れる所は多くない。夏だった気がする。数人の家族が観音開きのガラスの扉を開けて入って来て、その中に白い服を着て肌は透き通る様に白く、華奢な年の頃は十六、七の乙女がいた。瞳は大きく澄み、ちょっと生身の人間離れしていて、森の精やら女神を、地で演じられるような人だった。
家族は何やら、はにかんだ笑顔で彼女に気を遣って取り巻いていた。皆でベンチに座り、誰かがアイスクリームを買って来て彼女に与えた。
その時、思いもしない事が起こった。彼女の顔が歪み、毛物の様にそれにしゃぶりついたのである。白痴なのか、心を病んでいるのか解らないが、その容姿とともに、現実離れした世界を漂う人だったのである。美は剃刀の上を渡る風の様なものだと私は思っている。
- 石三つ道端に置き明日来る目印として絵筆を洗う
石三つ道端に置き明日来る目印として絵筆を洗う
私の歌である。今ではあまり見掛けなくなったが、私は現場主義の絵描きで、一枚描くのにひと月程モチーフに通う。様々に変化する光、空、自然との触れ合いから生じる感動を描く為にである。
薄暗くなり、帰り支度を始める時、私は手近な石を三つ拾い、画架の足元に置く。一米でも場所がずれると、翌日なんとなく違和感があるからである。
この歌を、北海道風景画館でご覧になった方から、原稿用紙一枚が送られて来て、数首の短歌が書かれていた。一目でそれはただならぬ歌人の作と見てとれた。その中の一首。
ここに来て明日も描くと目印に置く石三つ寄り添うが見ゆ
私の歌では寄り添うとは歌っていないが、橋本喜典先生の歌では、あたかも見て来た様に寄り添うとある。先生が、この言葉を紡ぎ出す為に、言葉にすがらなければ生きられない傷付き易い心で、どれだけ誠実に、そして謙虚に生きてこられたのだろうと思うと、今でも胸が熱くなる
- 庭に吾亦紅が咲いた。
庭に吾亦紅が咲いた。野にいくらでもあるが、ほとんどは白花で、赤紫色の自生は、この辺りではみたことがない。この花はもう十五年も前、友人が、病院で重い病を宣告され、何処へ行ったら良いのかも解らずふらふらと花屋に行き、そこで求めたと聞いた。「奥田さん要りますか?」とそんな話を伺いながらいただいたものである。その友人も亡くなった。
夕暮れがはやくなり肌寒くなったこの季節、ことさら美しく慎ましく心に沁みる花である。
- 画の第一義
画の第一義
まずは感動から始まるべきである。感動とはモチーフに対する畏敬の念と、自分の心を見詰める機会、つまり自己発見である。
風景にしろ人物にしろ、心洗われる様なものを見詰め、自分の卑小な美の認識を押し付けるのではなく、どこまでもモチーフから学び発見する事にその力を傾けるべきである。その意味において、神の創造物に接するごとくにである。
また、あらんかぎりの自分の精神にある崇高なものへの憧れ、弱く悲しい者への労り、つまりは愛を持って、困難な美の追求ということに、這いずりながらでも、一歩一歩近づかんとする事である。芸術は物を作る事ではない。精神を描く事である。自分の狭い世界を押し付けることではなく、心洗われながら生きる事である。
- 今、絵を描いている大豆畑の農婦と立ち話をしたが…
今、絵を描いている大豆畑の農婦と立ち話をしたが、畑の一部は水やけで葉が黄色くなり、今盛んに花が咲いているが、こんな気候は初めてなので、豆が取れるかどうかは解らない。うちだって解らないが、今年は倒れる農家があるだろう。そう言いながらもまた広大な畑の草を鍬で取って行く。
ああ、そうだなとふと思った。心配事はありながらも、日々に自分に課せられた仕事をコツコツと続ける。我々弱者には、他にやり様もないし、それが人生なのだろう。
- 絵画において重要な事は二つだと思う。
絵画において重要な事は二つだと思う。一つは自然、大きく言えば宇宙を反映したものであること。もう一つは、人の心を反映したものであること。とりわけその最高峰は愛であることは言うまでもない。私は絵画とは物ではなく、物と生命の中庸にあるものだと信じている。
- 聖の地の泉といえど庶民なる吾には賜えぬ遥けきものか
聖の地の泉といえど庶民なる吾には賜えぬ遥けきものか
病篤き母がルルド(奇跡の水)のことを詠んだ歌である。私はこれによってルルドを知り、いつかは訪れてみたいと思い続けていたが、数年前にそれが実現した。家内と娘が暮らすスペイン北部のバスク地方の小さな町から、二月に一日だけルルド祭りへのバスが出る。早朝のバスに私は乗った。満員であった。スペイン語が話せない私に皆は優しく、すぐに打ち解けた。数時間の後、夢に見たルルドの泉に立った。修道女ベルナデッタが女神を見た泉の上には立派な教会が立ち、ミサを最後部から背伸びして見た。
家内の同級生にルルデス(ルルドの英語、スペイン語)という友人がいる。夫がその地方では知られた画家で、私とも仲が良い。アリと言う。ハンサムな男だが、結婚後、背骨が曲がり始めた。昔で言う背むしであろう。ルルデスは、彼の体にいくらかでも良い様にマッサージを勉強し、また、その小さなサロンを持ち家計を助ける。子供がお腹の中にいる時、周りの人は障害を心配したが、彼女は「ハンディキャップがある子供でもいいの。」とあっさりと言い二人の子供を産んだ。
- ゴッホと言うと…
ゴッホと言うと、狂気の画家という印象を抱く方も少なくないだろう。うねる様な線描の絵を描き自らの耳を切り落とし、三十七歳で自殺した。ところが、厚い本数冊にも及ぶ彼のみすず書房の書簡集を読むと、激しくストイックな面もあるが、彼は理知的であり、自分より弱い立場の人々には、自己犠牲をも厭わない人間的な愛の持ち主である。私は彼の愛を思うとき、最初に思い浮かべるのが、マザー・テレサである。インド、カルカッタの街で、生き倒れた人々を、死を待つ人の家に担ぎ込み、その誰からも必要とされない人々が、イスラム教徒であるなら、クリスト者の彼女はイスラムのお祈りをする。一神教では考えられない事である。
若きゴッホは、ボリナージュと言う炭坑の街に伝道師として赴任した折、Fragile(こわれもの)と書かれた麻袋を纏い働く貧しい人々に涙する。小奇麗な服を着ていた彼は、自分の持ち物全てを彼らに与え、自らもボロ布を纏い伝道を始める。岸坑で事故があった時など、徹夜で怪我人の看病にあたった。彼は彼の主が思い描いただろう世界を生きた。しかし伝道師協会は、彼の行動は伝道師の品位を落としめる行為として彼を解雇してしまう。彼は一度だけ結婚生活らしい事をしている。相手は子連れの身重の娼婦シーン。家族は猛反対をするが、彼は彼女や子供を愛し守ろうとする。「女を捨てる男と、身寄りのない女と暮らすのと、どちらが人間的なのだ。」と彼は手紙に書いた。彼女をモデルにした「悲しみ」というスケッチは彼の言うとおり、若くも美しくもなく皮膚が垂れ下がった女が、膝を抱え裸で俯いている。そんな彼女もやがて彼を去り、元の仕事に戻り、彼は性病で入院する事になる。
芸術とは何か、それは愛であり、宗教であり、哲学であり、市井の名もなき人の日常であり、人生である。自然の素晴らしさに心を洗われることであり、人々のいじらしさに涙する事である。悲しみであり、失望であり、受容である。ゴッホの絵が類い稀な光を放つのは、彼が類い稀な愛の持ち主だったからである。
ゴッホの本名はフィンセント・ファン・ゴッホ。フィンセントと言うのは勝利者という意味で、ゴッホの生まれるちょうど一年前に生まれ、すぐに亡くなった兄の名でもある。
- レインボーフィッシュ
レインボーフィッシュ
スペインで暮らす娘は八歳になった。毎年冬のひと月程、私が出掛けて行く。髪はブルネットで、私から見れば街中を歩く少女と変わらないが、スペイン人から見ればやはり東洋的な印象を持つのかも知れない。国が異なれば、いろいろ暮らし振りが異なる。私は朝明るくなれば仕事を始め、夕方薄暗くなると川沿いの小路に散歩に出掛けるが、とにかく散歩をする人が多い。小さな街だが一時間二百人、三百人とすれ違う。そしてまた、皆歩くのが早い。かなり年輩の人でもあっと言う間に私を追い抜きたちまち小さくなる。私の様に水面を揺らす銀鱗に立ち止り、小鳥が枝を渡れば立ち止まるのを、やはり東洋人は変わっていると眺めているのであろう。
娘の通う学校の写真を見ると、書道をやったり、先生が着物を着て授業をしているものがあり、ユニークな教育をしている様である。クラスメートは十数人といったところ、白人ばかりでなく、黒人やイスラム教徒、娘の様に東洋系の血の混ざった者もいる。その中の一人の娘は、なんとか話が出来る様であるが、ほとんど動けず、ストレッチャーの様な物に乗って同じクラスで授業を受けているようだ。命もそう長くないように聞く。親御さんの気持ちを思うと心が痛む。今日はその子の家で、横になりながら見て楽しんでいた金魚が、水槽から飛び跳ねたところを猫に食べられた話を聞いて来た。さぞがっかりした事だろう。
娘が段ボールを切って輪にして、テープで留め、何かを作っている。それに巻き付ける白い紙に金魚や、虹色の魚と水草を描き始めた。娘は金魚鉢を作り、友人にあげようと思い立ったのである。そんな姿を見て私はハッとして、画家として深く反省させられた。画家は愛を描くべきである。
- 千枚を超える画を描いて来たと思う。
千枚を超える画を描いて来たと思う。新しい画を描き始める度に、今度こそ良い物を描こうと思う。楽観的と言うか間抜けと言うか、そんな事を三十年以上独り続けている。それは私が生きることであり、祈りでもある。
- 二階のアトリエの一つの窓には網戸があって…
二階のアトリエの一つの窓には網戸があって、換気の為に半開きにしておくことが多い。ここに新緑の頃になるとかなり大きな羽音をたててよろよろとカナブンが飛んで来て止まる。カナブンはこの辺ではそう見掛けないので、昨年のものの子供であるのかも知れない。親も同じ網戸に止まっていたなどとは露知らず、同じ網戸止まっているのであろう。庭ではエゾハルゼミの群れが賑やかに鳴いている。彼らも彼らの親が数年前、同じ様にこの庭で鳴いていた事を知らない。
- 私は捨て猫を見ると拾って来る癖がある。
私は捨て猫を見ると拾って来る癖がある。今回で五匹目だろうか。社会の歯車から外れたもの同士の共感があるのだろう。ペットショップの小奇麗なものより、その存在が心に沁みる。車を走らせていると道端に小さな白いものが動く。ああ、子猫だと思って車を止め、少しバックして掴まえようとすると、幅四十㎝程の側溝も飛び越せないでその中に落ちた。手の平に乗る子猫である。
帰り道、こんな事を子供がすれば、親は「お前は全くそんな事ばかりして、元の場所に戻しておいで」と、叱られた所であろうと苦笑したが、還暦の私は「芸術家にはこういう事が大事」「芸術家にはこういう事が大事」と、自分に言い聞かせた。
家に帰り以前魚を飼っていた幅六十㎝の水槽に入れ、哺乳瓶で子猫用のミルクを与えるが、なかなか口を開けない。無理もない話で、ちょっと前まで兄弟たちと母親の乳を飲んでいたのである。天国から地獄に落ちた様であろう。それでも飲まなければ命が続かない。無理矢理にでも飲ませる。三時間おきと聞くので、夜は無理だが、日中はそうした。
夜、インターネットのテレビ電話でスペインの八才の娘に見せると動物好きの彼女は眼を丸くして喜ぶ。お前が名前を付けろと言うと流石は現代っ子、すぐにAで始まるのは何々、Bでは何々と猫の名を検索し始めた。(日本語は話せず、私とは英語で話す)二十以上の名が候補に上がったが、ジョージにしたいと言う。それからジョージと呼ぶと二、三日も経つと遠くからでも返事をする。ミルクは自分からは飲まないので相変わらず口に流し込む。四、五日も経つと大分弱って来たが、私の手の平が好きで、そこに上ると喉を鳴らし嬉しそうである。目ヤニで眼も開かなくなったので、目薬を買って来て付ける。眠るとまた目が開かなくなるので、水で湿らせて、目を開ける。可愛らしかった猫は目ヤニとミルクで毛が固まりボロ雑巾の様な顔である。それでも私と彼の心は近づいて、彼は私を信頼し切っている。とうとう別れの時が来た。やっと這い上がる様にして彼は私の手の平に乗った。息が荒くなる。一時間程、何度も死にかけては息を吹き返した。最後は体をのけぞる様に伸ばし少し鳴いた。獣医でもない私は何も出来ず、一部始終を見守り寄り添った。死は嫌悪するものではなく、生と連続する荘厳なものだと、このボロ雑巾の様なジョージに教わった。彼は今、ポプラの大木の根元に眠る。いつか原子に戻ってその天辺まで上って行くだろう。無力な事は残念で悔しい事ではあるが、素晴らしいことでもある。苦しむものに寄り添う事ができるからである。
死に行くを腕にいだきて見とどけし小緩鶏は剥製となりて戻りぬ(宏江、母)
- 純粋意識
純粋意識
江戸時代の盤珪和尚の禅は不生禅と言うが、面白い説法がある。曰く、「人は皆仏心ひとつで生まれて来る。その証拠に、皆さんは私の話を聞きながら、外で鳴く烏の声、雀の声を聞こうともしないのに聞き分けている。チュンとカアを聞き違えることはないのである。それが不生の仏心で聞いている証拠である。仏心以外のものは全て我欲で、皆さんは我欲の方を自分だと思っている。」
私は画家なので、その事が仕事に照らして解る気がする。例えば白菊一輪を描くとする。私が描いているのは感動つまり菊に写った純粋意識(仏心)である。菊を我欲で描いていては芸術にならない。
いつだったか、ゴーガンとゴッホの絵が並んでいる展示があった。以外にも一見ゴーガンの絵が、絵の持つ力では上の様にも見える。セザンヌが、ゴーガン氏は私から手法を盗んだと言ったが、絵としての力はセザンヌと並べても勝るものがあると思う。さはさりながら、芸術性、精神性となると話は別だ。セザンヌ、ゴッホと、ゴーガンでは世界が異なる、前者が純粋意識なのに対して後者は我欲、小智つまりはゴーガンの想像力の範中である。ゴーガンはアルルの黄色い家で短期間であったがゴッホと共同生活をしながら、ゴッホに想像で描くことを勧めた。素直なゴッホはいくらかそれを試みたが、やはり写生に戻って行く。写生ということは、純粋意識に入る一つの有力な方法であると私は思う。ゴッホは、創作には天上の光が必要だと言った。天上の光とは、純粋意識ではあるまいか。
- 初雪
初雪
居間の前には十坪程の池があって、彩りに何匹か錦鯉を泳がしている。昨夜は大分冷え込んで、半月よりやや欠けた月が水面に映っていた。部屋の灯りを消して池に向けて置く椅子に座りながら、月の明かりの中で鯉の赤や白の色はどの様に見えるのだろうかと思ったが、鯉は池庭でじっとしているらしい。
今年の初雪は例年より半月程遅く、十一月六日となった。たいてい私は初雪をこの椅子に座って池を眺めながら見る。冬が好きというわけではないが、この時が来るのを楽しみにしているところがある。雪の一つの結晶が空から落ちて来ると水面に映る。それはあたかも水底から水面に向って湧き出している様に見える。空から降る雪と、水底から湧き出して来る幻の雪の二つが次第に近づき、水面で一つになる。一つ一つの雪がそれを繰り返し繰り返し、静寂の中で時を刻む。始めてそれを知った時は嬉しかった。絵とはその様な発見、感動を描くのである。
- 芸術に至る過程
芸術に至る過程
一、昼ながら幽かに光る蛍一つ孟宗の藪を出でて消えたり
北原白秋の歌である。一幅の絵画を見ている様である。実際に画にすれば良いものになるだろう。
白秋はこの場面を実際に観ていたと思う。そして観た瞬間に、どの様な形になるかは全く解らない段階で、いい歌になると確信したと思う。それは宇宙の、あるいは自然の創造主が、直接彼に語りかけた瞬間であった。知性も才能も経験も常識も入り込む暇のない瞬時の出来事だった。
三十一文字の中で時間を取り込み、蛍を空間の中を移動させた白秋の作歌の力量、人間的な気品があったにせよ、この歌を珠玉の一首にしたものは白秋と神(お働き)との直接の対話に他ならない。西行法師にこんな歌がある。
何事のおはしますかは知らねども かたじかなさになみだこぼるる二、画の制作についても、全く同じ過程を辿る。一つ加えるなら、神からの啓示はもう一度あると言うことである。モチーフに巡り会った最初の感動を頼りに、全ての要素を一度分解し、カンバスという虚構の時空に再構成して行く、ここではその技量にも増して作家の人間性そのものが問われる。つまり作品は人なりである。さらに言えば、良い作品にはこの過程で、作者が思いも寄らない感動がある。突然に作品に命を吹き込む様な道が示されるのである。作者から言えば作者を越えた天上からの光である。いわば創造主の介入である。
これが工芸、例えば陶芸であれば、陶器を火の中に入れることを代用としている気がするが、芸術の場合、作家として出来うることを全て行った上で、ひたすらに待つ。それは祈る行為に似ているのではないかと思う。三、子供の画に魅力があるのは、ファーストインスピレーション、モチーフの印象、感動を素直に表現しているからで、経験や技術、常識、裏心がないだけ、モチーフをいじくり回さない。つまり作品が汚れないのである。
山下清氏の絵画が素晴らしいのも同様の理由による。氏を日本のゴッホと呼ぶ人もあるが、紙を貼り付けたものが、ゴッホの線描に似ているものの、全く別の領域である。ゴッホの場合、人並み以上の知能もあり宗教心、弱者へのいたわり、勤勉さ、自然への愛、どれをとっても最も人間的な優れた素養を持つ。その上で山下氏の様に汚れない心を持ち続けた。
彼の絵が今も光を放つのは、始めのモチーフからの感動の強さを、創作の過程でも失うことなく、第二の神からの直接の啓示、天上の光を受け入れるに値する、希な人間的愛の持ち主であったということであろう。
科学が智で解き明かそうとするものを、芸術は智以前の不思議として、祈りに昇華しようというのである。
- 母の歌
母の歌
遠く見る眼差し慣れた母なれば微笑みながら夢を語りし
指に出すオーラで母を治すよと母が眠れば指先向けし
もう行けといつも促す病む母が二度言いたるに涙止まらぬ
片腕はまだ動くよと母は言い吾が肩揉めり揉むにまかせぬ
棺桶の蓋を外して母を描き疲れたるとき並びて眠る
度の合わぬ眼鏡を掛けし母なれば柩の中に持たせて閉じし
息止みし己が顔を描かせて母はその子を絵描きとなしぬ
母の骨みるを拒めば弟と父らで拾い壺におさめ来
アイバンクの登録言いし母の眼の角膜二つ焼いてしまいぬ
吾が母の口の黒子は左かと夜中に起きてデスマスク見る
我がうちに生き行く母の好みなる切り干し大根食べてみるなり
髪を梳く母を思いて髪を梳く母の髪残る母の櫛にて
この世に母がいないことを思い出さない様に眠り込んでしまおう
忘れいし母の声なり出来ますと言うに目覚めて闇に目を開く
我の血の香りに寄りし蚊の一つ潰せし後に母と気付きぬ
「デスマスク」